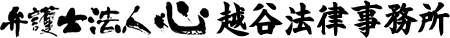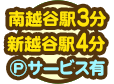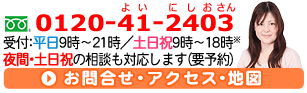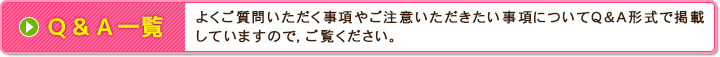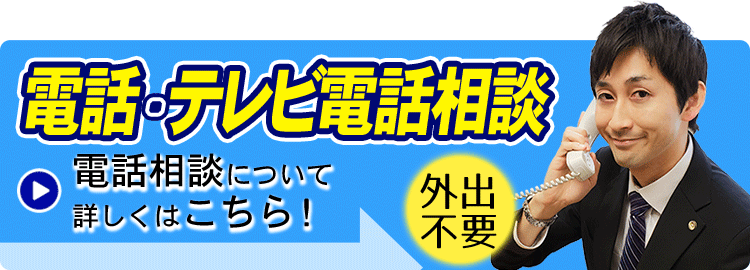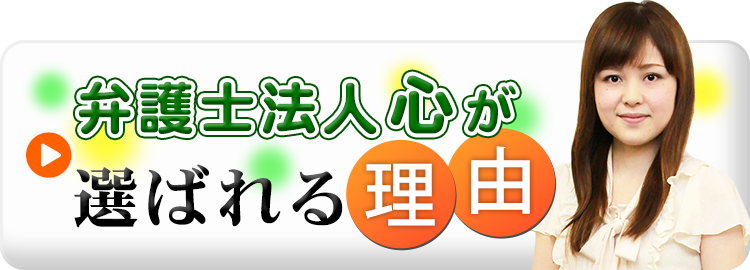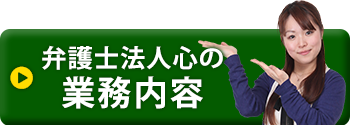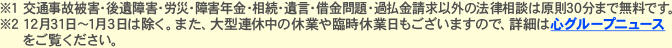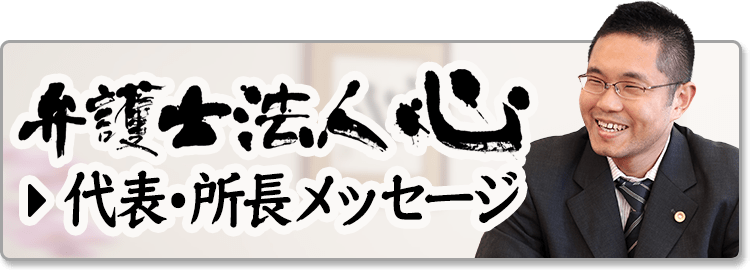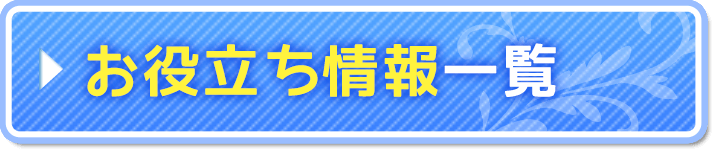相続手続きの種類
1 相続手続きとは?
相続手続きは、故人(被相続人)が生前有していた相続財産(遺産)について、相続人に移していく(あるいは移さない)手続きのことです。
まずは、被相続人の遺産に何があるのか確認し、どの相続手続きをしていくのか、考えることになります。
遺産としてイメージしやすいものとしては、不動産や預貯金、株式がありますが、債務(借金)も含まれますので、その点に注意が必要です。
2 相続放棄
まず、相続放棄について説明しておきます。
相続放棄は、相続をしないという選択肢です。
遺産のうち、借金(マイナス)が大きすぎて、預貯金など(プラス)のものでは到底支払いきれない場合に、はじめから相続人ではなかったとしてもらう手続きです。
このほか、被相続人と関わりたくない相続人が相続放棄を選択することもあります。
3 限定承認
遺産の中の借金が大きいけれども、相続放棄をするのではなく、金額的にプラスの範囲内でマイナスを支払う、ということができ、それが限定承認です。
4 遺言
遺言がある場合、基本的には、故人の最後のメッセージである遺言に基づいて、それを実現していきます。
公正証書遺言は公証役場に保管されていますので、確認しましょう。
自筆証書遺言の場合には、検認手続きを経て、相続手続きを進めていきます。
相続人で協議して、遺言とは異なる遺産分割をすることもできます。
遺言がない場合で複数の相続人がいるときにも、遺産分割協議を行うことになります。
5 遺産分割協議
複数の相続人で、遺産についてどう配分するかを話し合って決める手続きです。
例えば、不動産であれば、誰か一人が所有することにして、その分、他の相続人に代償金を支払うという代償分割や、相続人の複数で共有するという共有分割、売却を行った上で、その売却代金を分ける換価分割という方法があります。
そのような話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を起こすことになります。