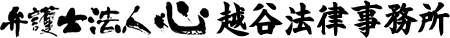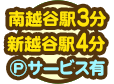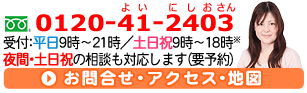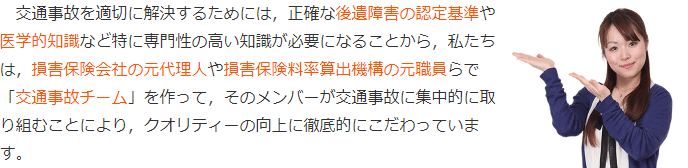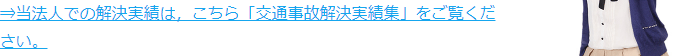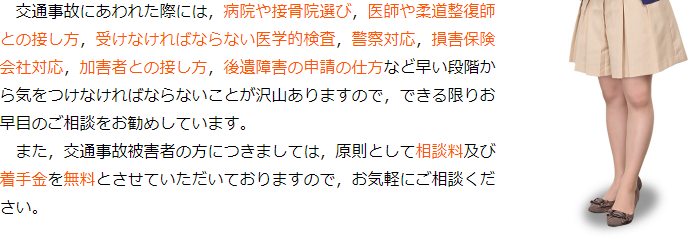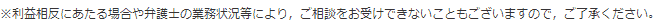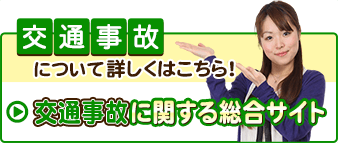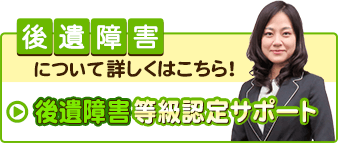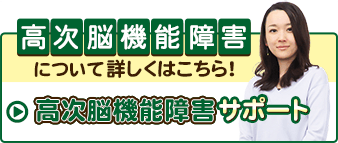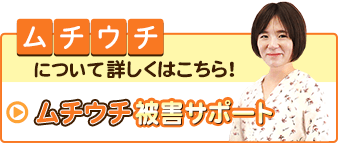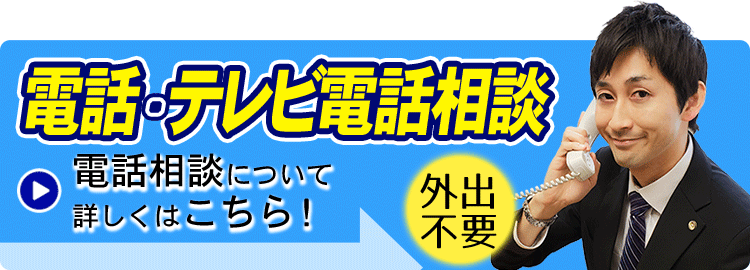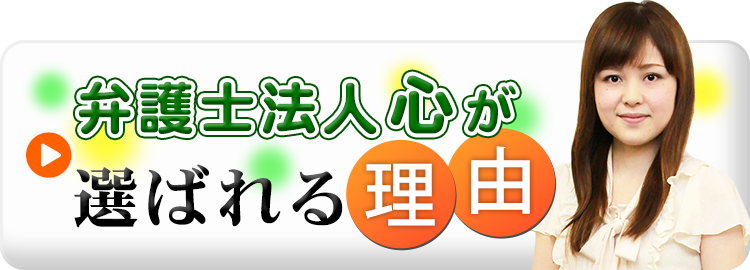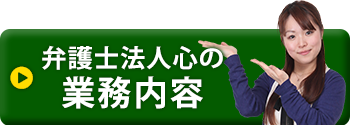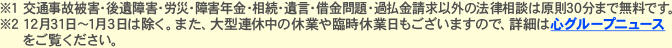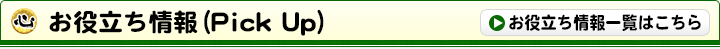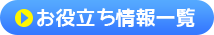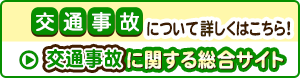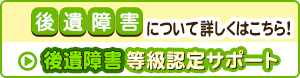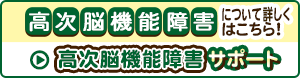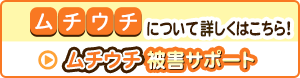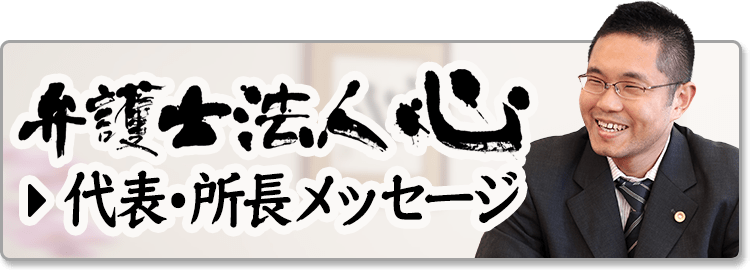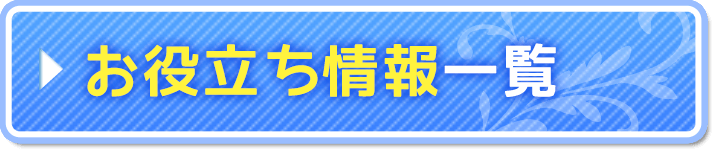交通事故・後遺障害
交通事故に遭った直後から弁護士に相談するメリット
1 通院についての適切なアドバイスを受けられる

交通事故に遭い、適切な賠償を受けるうえで極めて重要になるのが、初動の通院です。
例えば、事故から2週間過ぎても通院をしなかった場合には、その後に通院して受傷したと訴えたとしても、事故との因果関係がないとして、相手方保険会社などから慰謝料の支払いはおろか、治療費の支払いですら対応してもらえないことがあります。
このような場合には、法的にも事故と関係のある受傷であることを立証していくことが非常に困難になります。
他にも、病院への通院頻度が30日以上空いてしまうと、大した怪我ではない、すでに怪我が治っているのではないか、といったことから相手方保険会社から早期の打ち切りを打診される可能性も高くなってしまいます。
早期に弁護士へ相談することによって、どのような通院方法や通院頻度が適切なのか、といったことについてアドバイスを受けられ、適切な治療や慰謝料の支払いを受けられるよう対処することが期待できます。
2 賠償のため適切なアドバイスを受けられる
また、例えば、被害者が自転車の運転者や歩行者の場合には、スマートフォンが破損したり、衣服が破れたりといった携行品・着衣損害が生じることが多いかと思いますが、損傷した携行品や着衣の画像を撮らずに捨ててしまうようなケースもよく見受けられます。
携行品や着衣損害を損害として請求する場合には、どのような損傷が生じているのかという点については、被害者側で立証する必要があるため、画像を取らずに携行品や着衣を処分してしまったような場合には、賠償金の支払いを拒否されることがあります。
このように、事故直後に適切な行動を取らなければ、相手方保険会社から治療費や賠償金の支払いを受けられなくなってしまう可能性があります。
3 交通事故に遭ったらすぐに弁護士に相談を!
上記で見たほかにも交通事故の直後の対応を誤ってしまえば、適切な賠償を受けられなくなる危険性は多く潜んでいます。
事故に遭ったらできるだけ早くに弁護士に相談することをおすすめいたします。
交通事故に遭われた際の警察対応
1 交通事故が起きたら警察に必ず通報する

交通事故が起きた際には、たとえ軽微な接触事故であっても必ず警察に通報し、交通事故として報告を行いましょう。
警察に通報せず、交通事故としての処理がなされなかった場合には、その後相手方に修理費や治療費等の請求を行った際に、事故として処理されていないことを理由に支払いを拒否される危険性が出てきます。
特に、車両同士の接触が生じていない非接触事故の類型では、警察に通報することなく解散してしまうケースも多いかと思いますが、回避の際に首を痛めたといったことで後日通院が必要になることも多くあります。
そのため、非接触事故の場合でも、警察に通報するかどうかはしっかりと判断した方が良いです。
2 警察には自身の認識をしっかりと伝える
警察が現場に到着した際には、警察から事故状況についての説明を求められることになります。
その際には、自身が認識している事故状況について、しっかりと警察に伝えるようにしましょう。
というのも、事故直後の警察への説明は、その後の実況見分調書の作成等に大きく影響を与えるものになります。
そのため、自身の認識を警察に伝えなければ、相手方の言い分ばかりが反映され、自身の認識とは異なる事故状況として記録されてしまう可能性があり、過失割合の交渉等を行う際に不利になる可能性がでてきます。
3 怪我を負ったら人身事故届を出した方が良い
事故で怪我を負った場合には、基本的に人身事故届を出した方が良いです。
人身事故届を出さなかった場合には、起きた事故は物損事故扱いとなりますので、後日相手方に治療費等を請求した際には、今回の事故で怪我は生じていないはず、怪我が生じたにしても大した怪我ではないはずといったことを言われ、支払いを拒否される可能性があります。
また、人身事故届を出さなかった場合には、かなり細かく事故の状況等が記載された実況見分調書等の刑事記録が作成されないため、ドライブレコーダーがないような事故の場合、そもそもどういった事故であったのかが分からなくなってしまう可能性もあります。
4 警察対応に困ったら弁護士に相談を!
上記のとおり、事故後の警察対応は、その後相手方と行う過失割合等の交渉に大きく影響するものになります。
事故から時間が経てば経つほど警察に取り合ってもらえなくなってしまう危険性が高まりますので、迅速に対応を行う必要もあります。
そのため、どういった対応をすべきなのか、弁護士に早い段階で相談することをおすすめいたします。
交通事故の問題を解決するまでの流れ
1 解決までの大まかな流れ

交通事故にあった際に賠償金の支払いを受けるまでの流れとしては、まず損害額を確定させ、確定した損害額を相手方に請求して交渉を行い、交渉がまとまらなければ訴訟等の法的手続きを経て賠償金を受け取るというものになります。
個別の事案によっては、順番が前後したりする可能性もありますが、多くの事件は上記のような流れになります。
以下で、それぞれの過程について詳しく見ていきましょう。
2 損害額を確定させる
まず、賠償金を請求するにあたっては損害額を確定させる必要があります。
例えば、自動車で事故にあったのであれば、修理工場に見積りを行ってもらうなどして修理費用や代車費用等の金額を確定させます。
また、怪我を負ってしまった場合には、通院が終了となった時点で治療費や交通費、通院慰謝料といった損害額が算出できるようになります。
仮に後遺障害が残ってしまったような場合には、後遺障害申請を行い、後遺障害としての認定を得られれば、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が算出できる状態になります。
もし、自分にも過失があるような事故の場合には、今回起きた交通事故の過失割合についても検討する必要が生じます。
このように、自動車の修理や怪我の治療を進めていき、相手方へ請求すべき損害額を確定させるのが、賠償金を受け取るための第一歩になります。
3 相手方と交渉・訴訟等を行う
次に、損害額が確定出来たら相手方に対し、こちらが算出した損害額どおりの賠償金を払ってもらうよう請求して交渉を行います。
勿論、相手方としても今回の事故で妥当と考える損害額を算出するため、どちらの損害額が正しいのか、話し合いをすることになります。
交渉してお互い合意ができたのであれば、相手方より賠償金の支払いを受けて一件落着となりますが、お互いの主張が並行線のままとなり、話し合いでは解決できない場合も少なくありません。
そのような場合には、第三者である裁判所等に対してどちらの主張が正しいのか判断してもらい、妥当な損害額を決めてもらいます。
4 弁護士に相談することをお勧めします
流れだけ見ると簡単そうに見えますが、事件によっては細かい損害額の計算等で争いになることがあり、算出の際には専門的な知識が必要になるケースが多くあります。
また、交渉についても基本的には保険会社を相手にしなければならず、自身で交渉を行おうと思っても、交通事故事件の知識量に差がある状態で話し合いをすることになってしまいます。
弁護士に相談すれば、損害額の計算から相手方との交渉、場合によっては訴訟についての対応もまとめて任せることができます。
交通事故にあった場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。